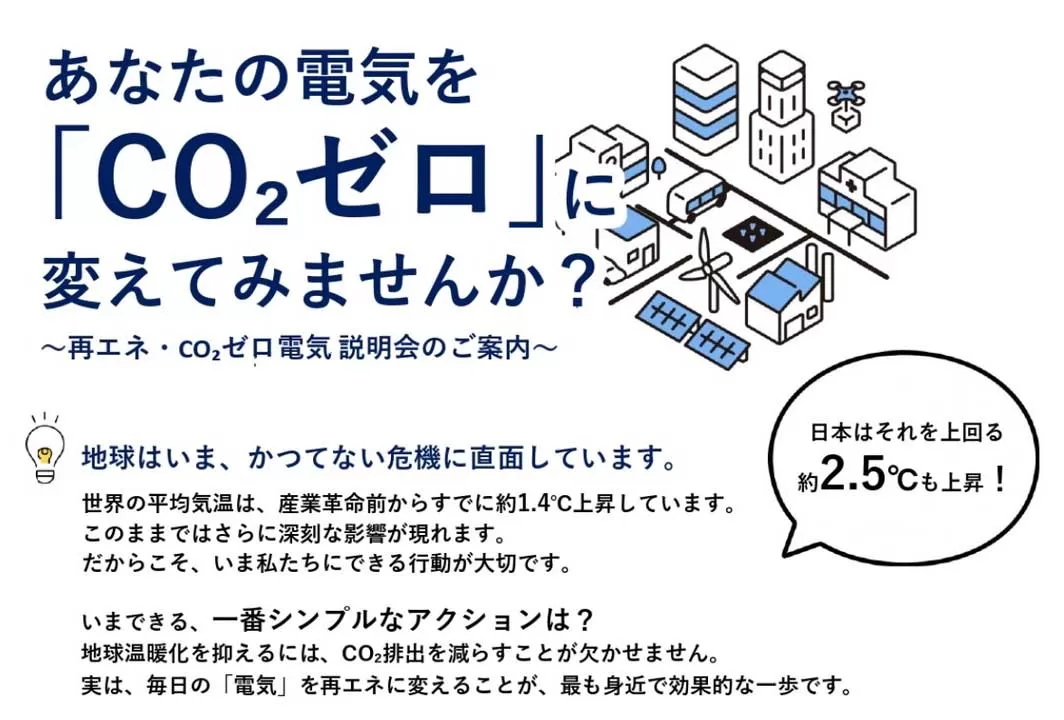【お問合せ内容】
時給1100円越えのニュースが流れているが、個人事業主が多い五島市にて事業者の懐事情は「過度な引き上げは中小企業への経営に打撃を与える」ものと考えられる。行政として民間事業者含め個人事業者への直接的なテコ入れはかなり難しくハードルの高いものでしょう。
賃上げは事業者泣かせ、市として最低賃金値上げに対しどのように支援対策を講じていくのか考えをお聞かせください。
回答:
最低賃金の引き上げは、労働者の生活の質を向上させる一方で、中小企業においては人件費の増加による、経営環境が悪化することも予測されます。
本市では、中小企業の皆様への経営支援策として、金融機関の協力を得て、低金利での融資を円滑に行う「五島市中小企業振興資金融資制度」があります。
この制度は、十八親和銀行、福江信用組合、福江商工会議所または五島市商工会への申込みを経て、貸付が決定されます。これにより、事業経営に必要な資金の融資を受けることができますので、経営の安定化を図るためにもぜひこの制度をご活用いただきたいと考えております。
本市としましては、今後も「五島市中小企業振興資金融資制度」の周知を図ってまいります。
また、経営の安定化には売上高の増加なども大事になることから、販路拡大に関する支援策などに加え、生産性の向上を目的とした従業員のスキルアップや能力開発支援についても、検討していきたいと考えています。以上、ご回答申し上げます。(五島市 産業振興部 商工雇用政策課)
五島市の回答に私なりの疑問点
五島市の回答を検証するため、回答いただいた支援策が、最低賃金引き上げという課題に対して具体的かつ実効性があるかを多角的に評価する必要がある。以下、検証してみた。
ステップ1:既存の支援策が現状に適しているか?
まず、市が回答の柱としている「五島市中小企業振興資金融資制度」が、今回の賃上げ問題に対して本当に有効な対策と言えるのかを検証してみる。
- 制度の利用実績と条件の確認融資制度が実際にどの程度利用されているのか、また、金利や保証料、返済期間などの条件が、賃上げで苦しむ事業者にとって本当に利用しやすいものになるのかを確認する。この制度は市のホームページで公開されており把握できる。もし条件が厳しかったりすれば、この制度だけでは不十分だと指摘する。
- 「資金繰り支援」と「賃上げ原資の確保」は別問題この融資制度は、あくまで事業経営に必要な「運転資金」や「設備資金」を低金利で貸し付けるものであり、賃上げの原資を直接的に補填するものではない。つまり、「借金をして賃金を上げる」ことを促すのであり、根本的な収益構造の改善には繋がらない。この点を踏まえると、融資制度は一時的な資金繰り対策にはなっても、賃上げに対応するための恒久的な解決策とは言えないのだ。
ステップ2:「今後の検討」の具体性を問う
次に、回答後半にある「今後の検討」部分について、その具体性と実現可能性を検証してみる。
- 販路拡大支援の具体策は何か?「販路拡大に関する支援策」とありますが、具体的にどのような支援を想定しているのかが不明確だ。例えば、ECサイトの構築補助、物産展への出展支援、ふるさと納税返礼品への採用拡大など、具体的な施策がなければ「検討する」という言葉だけで終わってしまう。販路拡大支援に該当する業務は物産協会等の加盟店に限られ、1次産業、6次産業のみと限られる。最低賃金の賃上げは全ての業種(小売業・製造業・サービス業・飲食業・介護事業など全ての職種が当てはまるのである)。
- 生産性向上支援の具体策は何か?同様に「生産性の向上を目的とした従業員のスキルアップや能力開発支援」についても、具体策がない。デジタル化を推進するためのITツール導入補助金、専門家による経営コンサルティング、従業員向けの研修プログラム提供など、具体的なメニューがなければ事業者は利用できないし興味もわかない。
ステップ3:国の支援策との連携は考慮されているか?
最後に、市独自の施策だけでなく、国が提供している支援策を事業者に周知し、活用を促す視点があるかを検証します。
- 「業務改善助成金」の周知と申請サポート国は、最低賃金の引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者向けに、生産性向上のための設備投資などにかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金」という非常に有効な制度を設けています。市の回答にはこの制度への言及がない。市の役割として、このような国の手厚い支援策を積極的に事業者へ周知し、複雑な申請手続きのサポートを行うことこそ、直接的な支援に繋がるのではないのか。この部分が欠けている点が、市の支援体制の課題であると指摘。
まとめ:五島市回答を評価
五島市の回答は、既存の融資制度の案内と、今後の施策の方向性を示すにとどまってしまった。しかし、賃上げという喫緊の課題に対し、融資制度は直接的な解決策とは言いにくく、今後の施策も具体性に欠けていた。
この回答を本当に検証するためには、市民や事業者が、
・「融資ではなく、収益を上げるための直接的な支援が欲しい」
・「『検討する』ではなく、いつ、どのような支援策を始めるのか具体的に示してほしい」
・「国の『業務改善助成金』のような、もっと直接的な支援策を市も紹介・サポートしてほしい」
といった声を、議会やパブリックコメントなどの場で行政に届けていくことが重要だ。行政の回答を鵜呑みにせず、具体的な行動を問い続けることが、実効性のある支援策を引き出すための鍵だと思う。

結局は物価高騰(材料・燃料費等)は人件費増と同じだと考えた場合、事業者は商品やサービス内容の価格値上げで対応するのが一般的なのである。最低賃金アップに対する税金でのテコ入れは容易に出来るものではないのである。これが私の考えである。
実はこの質問は、経営戦略会議にて大賀副市長が発した内容なのである。
令和7年8月4日(月)
注目したいのが最低賃金であり、全国平均で1,100円程度になるようである。現在長崎県は953円であり、市内民間が対応できるか危惧される。地域経済の活性化は私たちに課されるものであり、それぞれの所管課で予算化も含めて検討していただきたい。
また。。。
人事院勧告が出されると思われる。4年連続でのアップとなる見込みで、3%アップという報道もある。
との話題にも触れられていたが・・・・・
人事院による報酬アップに関しては市職員以外にも影響をもたらします。特別職報酬(市長・副市長・議員)も便乗してアップされるのです。
サービスや働き度合いに反比例しての賃金アップなのです。
【2日】長崎県の最低賃金1031円 過去最大78円引き上げ 発効日は12月1日 審議会答申(長崎新聞 2025/09/02)
長崎地方最低賃金審議会(会長・深浦厚之鎮西学院大教授)は2日、2025年度の長崎県の最低賃金を現行から78円引き上げ、時給1031円にするよう倉永圭介長崎労働局長に答申した。発効日は12月1日。引き上げ額は時給方式となった02年度以降で最大。中央最低賃金審議会が示した目安額64円を14円上回った。
審議会(本審)に先立って同日開いた第5回専門部会(部会長・林徹長崎大教授)では前回までと同様、労使各委員の主張が一致せず、学識経験者らで構成する公益代表委員が78円の引き上げと12月1日の発効を提示。使用者側委員3人は反発し、全員退席。その後の採決で部会長を除く、5人全員が賛成した。
本審の採決では出席した委員14人のうち、使用者側委員(4人)が「反対の強い意志を示すために退席する」と表明。深浦会長は「採決に参加してほしい」と促したが、「考えに変わりはない」として退席した。会長を除く公益代表委員4人と労働者側委員5人の計9人全員が賛成した。
中央審議会が決めた25年度の引き上げ目標は全国平均で63円。経済情勢などで都道府県を三つに分けた区分のうち、長崎県など地方部13県のC区分は64円としていたが、長崎県や秋田(引き上げ額80円)、岩手(同79円)など各地方審議会で目安を大幅に上回る答申が続出している。
九州・沖縄では福岡を除く7県がC区分。1日までに答申された県のうち、時給は佐賀1030円(引き上げ額74円)、鹿児島1026円(同73円)、宮崎と沖縄1023円(同71円)となっている。

 求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供
求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供