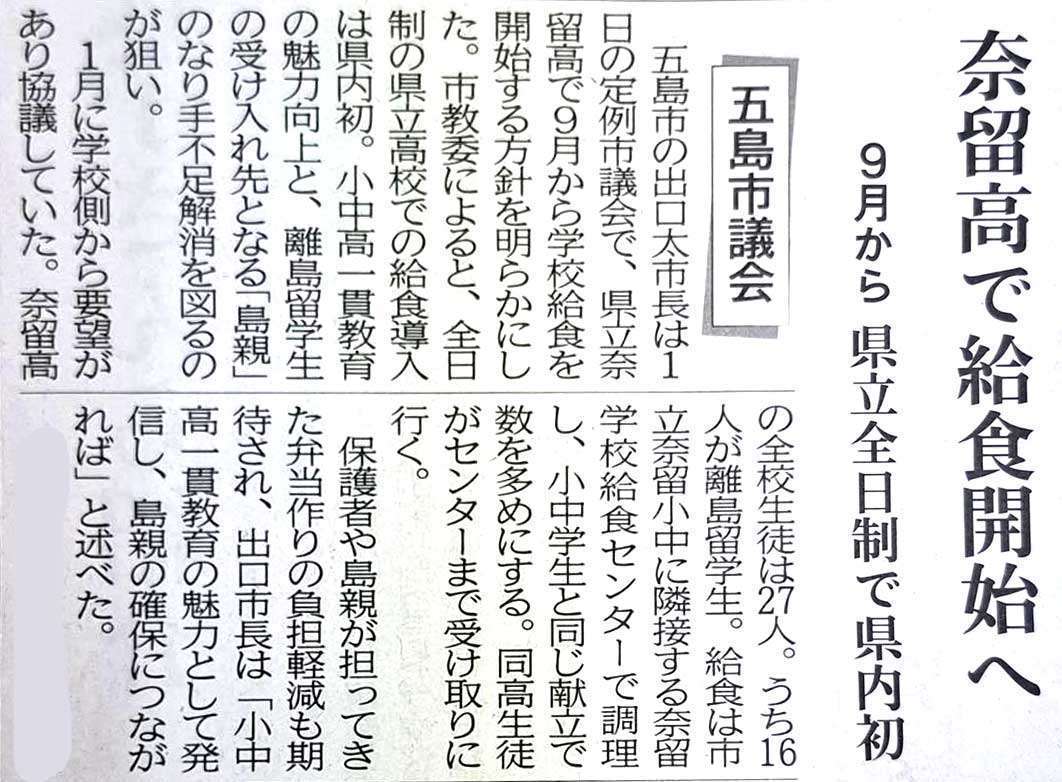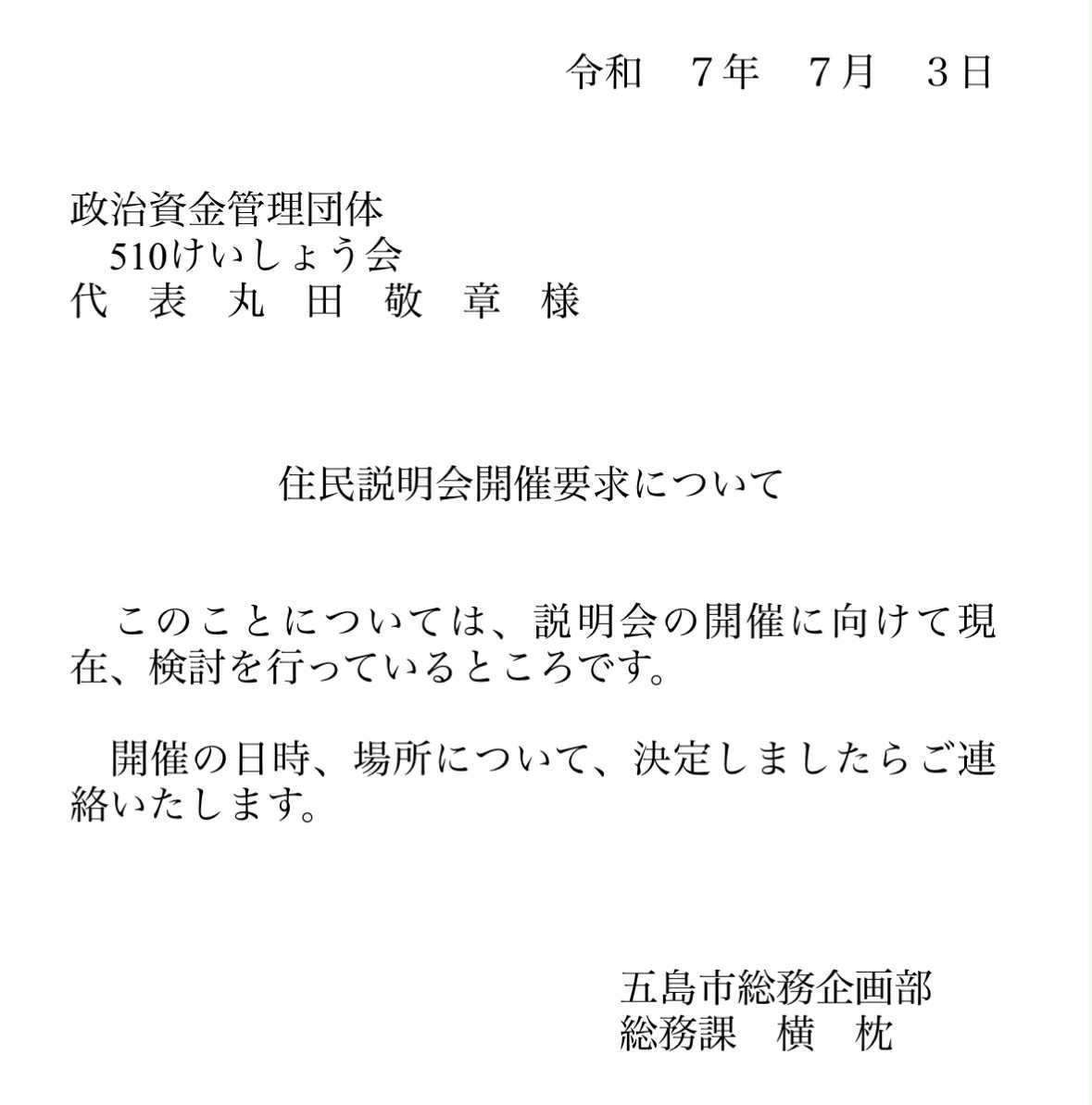住民監査請求ってなに?、「地方自治体のお金の使い方や契約などが違法または不当だと住民が判断したときに、監査委員に対してその是正や責任追及を求める制度」だそうだ。
これ、全うしている?五島市監査委員は?
五島市が支払った先は事?者ではなく【長崎県国民健康保険団体連合会】へ支払った。違法でも不当でもない!
小学生か(笑)?市監査委員は介護給付金の支払先が長崎県国民健康保険団体連合会だと主張したから、新たな問題発覚に対し、被保険者である(国民健康保険加入者として)五島市民の一人としてきちんとやれ!とメール送信してやった。
1. 形式審査と実質審査の問題について検証してみた。
本件の核心は、給付がされた行為自体ではなく、給付の対象となったサービスが実際に適切に行われていたかどうかが本質なのにも関わらず、給付実態の妥当性の検証を、形式上の審査やら支出手順やらが適当にしたんだから、それでOKとするのであれば、住民監査制度の制度やルール、取り組みなどが本来の目的や意義を失い、形式的なものになってしまう状態になるのである。
監査委員は、①市から事業者への直接の支払いではないこと 、②国保連合会への支払いは適正な手続きであったこと を主な理由に請求を棄却した。これは、支出の「プロセス(形式)」に違法性がないという点を強調したものに過ぎない稚拙な監査で済ませたのである。
しかし、住民監査請求は、そのプロセスだけでなく、支出の原因となった「行為」が不当である場合も対象なのだ。
事実、夜勤職員が24時間常時対応義務を故意に損なっていたのだから、それは給付対象となるサービスが提供されていない状態を意味し、その対価として公金が支出されること自体が「不当」であるという実質的な議論こそが本質なのである。
2. 支出の責任の所在と最高裁判決の解釈について検証してみた。
監査委員は「実際に事業者へ支払ったのは市ではなく連合会である」ことを根拠に、「市の支出ではないから対象外」と結論づけたけど、連合会への支払いは市の支出負担行為によるものであり、委託先が支払ったというだけで市の責任は消えないんじゃないの?
国保連合会はあくまで市の委託に基づく「審査支払機関」であり、給付費の財源は市が負担している。したがって、最終的な支出責任が市にあることは明らかなのだ。監査委員会が「市の直接の支出ではない」と強調するのは、責任の所在を曖昧にするための、過度に形式的な論法と受け取られても致し方ない。
S51年の最高裁判決を引用してるが、これ、結局は、何でもかんでも住民訴訟の場合の請求がなんでもとおるわけじゃないぞと言っているだけにすぎず、実態として、違法性や不当性が認められれば対象となるのは当たり前の話であって、全く別の話。
監査委員はこの判例を「間接的な行為は対象外」という論拠として用いているが 、これは判例の趣旨を拡大解釈している可能性があり、職員の不適切な行為によって市の財産(税金や保険料)に損害を与える蓋然性が高いのであれば、それは十分に監査の対象となり得ると考えるのが自然なのではないのか?
3. 保険者としての市の責任と調査の深度について検証してみた。
「連合会が審査し、五島市はその支払いを行った。よって五島市の責任ではない」とする論理は、保険者責任の放棄じゃないの?…介護保険法42条の2第8項にばっちり書いてある。
監査結果にもある通り、介護保険法第42条の2第8項は、市町村(保険者)が「指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする」と定めているのだ 。
市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額及び第七十八条の四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
連合会に審査を委託しているからといって、市の最終的な監督・確認責任が免除されるわけではないのだ。
請求人の主張の核心である「夜勤職員が外部者を招き入れ、業務を事実上放棄」していた点について、監査委員会は市の調査報告(勤務表や日誌の確認)を追認するだけで 、自ら事実関係の解明に努めた形跡が見られなかったのだ。
「記録がある」ことと「実際にサービスが適切に提供された」ことは同義ではなく、疑惑の核心に迫るための踏み込んだ調査を行わず、性善説に基づいて書類の整合性のみで「問題なし」と結論付けているのであれば、それは監査機能の放棄にあたり、短絡的であるとの批判は免れられないのである。
4. 定員超過の事実と監査結果の致命的な矛盾について検証してみた。
「意見」部分では、定員9名で届け出ていたにもかかわらず、10名が入居していたという「条例違反」の事実を認定している。にもかかわらず、「損害なし」「不当支出ではない」とした監査結果との整合性が全く取れていない。正直、アホなのか?と疑ってみたくなる。
これは、この監査結果における最大の矛盾点を残してしまったのだ、論理的な破綻と言っても過言ではない。
定員超過は、指定基準を定めた条例(五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例第124条 )に違反する重大な過失なのである。
この定員超過という事実により、そもそもこの期間の介護給付費の請求自体が、根本的に不適切・不適法であった可能性が極めて高くなったわけであり、これは「過誤請求」に該当し、当然、市が支払った給付費は「過誤支出」として返還を求めるべき対象となり得る。つまり、市に明確な「損害」が発生していることを示唆してしまったにもかかわらず、
監査委員はこの重大な事実を、法的拘束力のない「意見」として付記するに留め 、結論部分では「市に損害も生じていない」 と断じています。これは自己矛盾であり、監査の結論そのものの信頼性を根底から揺るがすものなのだ。この点を重要でないように結論付けたことは、監査の意義を自ら放棄するに等しい行為に当たる。
まとめ
以上、述べさせていただいた私の考え方は、単なる感情的な批判ではなく、法的根拠と論理に基づいた正論だと思っています。今回の監査結果は、住民監査請求制度の趣旨を没却し、住民の声を形式論で退ける典型例と言えるのです。
特に、自ら認定した「定員超過」という重大な違法行為と、「損害なし」という結論との間の明らかな矛盾は、監査そのものの体をなしていないとさえ評価されかねないという、現在の五島市行政の深刻な問題点を問題提起いたします。
このような回答がまかり通れば、行政の財務会計に対する住民の監視機能は著しく低下し、制度への信頼が失われるという懸念は、住民一人一人が真剣に考えねばならないし、結果として自分たちに不利益な行政業務となるわけです。
総じて、510けいしょう会による監査請求の主張を尊重することなく、「行政に問題なし」とだけした態度は稚拙であり、
「行政の説明責任だとか二度と言わないでください」と言いたいような監査結果であった。
これがまかり通る五島市です、「どうぞ、勝手にやれ! 不倫もどんどん勝手にやりまくれ!!」と言ってやりましょう。

 求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供
求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供