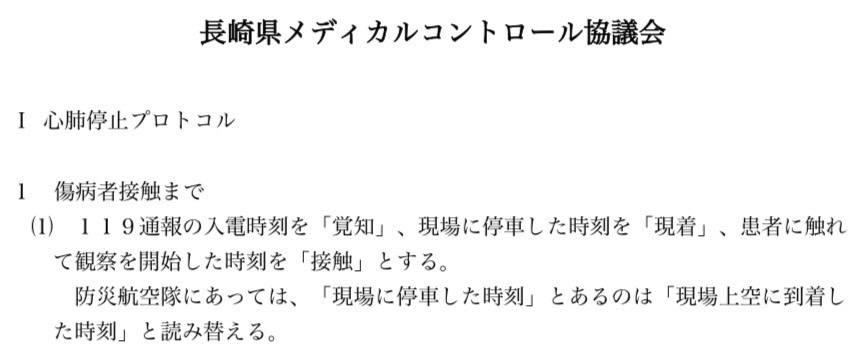お馴染みとなった前回までのおさらい
前回⑥までのおさらい新規追加分です。⑰〜
⑰救急隊や救急救命士などが現場で迅速かつ的確に対応するため、国の標準プロトコルに準拠した内容で定められた「一連の判断基準や手順書という「プロトコル」が各都道府県に存在。
[長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコル]→つまり、ガイドライン、マニュアル、取扱説明書。プロトコル(手順書)に従えば業務も統一され効率的、適切な処置、的確な救急活動となる。
原則、厳格に遵守しなければならない。長崎県内の救急隊は、このプロトコルを遵守した救急活動がなされている。
⑱救急業務の実施に必要なプロトコルは、国が制定した標準プロトコルを参考にして長崎県MC協議会がプロトコルを策定する。県レベルの協議会の下に、下五島地域MC協議会が組織されている→救急医療体制をコントロールしている。
⑲救急業務の実施に必要なプロトコルの内容は、日本全国だけではなく国境を超えた医学研究、技術の進歩、医学的見地、専門家の推奨事項に基づくプロトコルであり、最新の医療知識・エビデンスに基づいて随時改訂・反映され定期的に更新されている。全国各地域の実情により若干の相違があるとしても上位法(法形式)に救急救命士法が制定されており原則的に全国一律。国の標準マニュアルと類似・調和→医学や医療などの発展進歩に比例した「最新の救命するための虎の巻」。言い換えれば、※救急業務に関して最新プロトコルの手順を超える最善の救命方法や活動手順は存在しないのである!
⑳救急救命士による早期のアドレナリン投与は、心肺停止患者の救命率向上や脳機能の予後改善に繋がる。救急救命士は傷病者への接触から10分以内の早期アドレナリン投与が重要。厚労省が早期投与を可能にするための実証事業開始し、より早期のアドレナリン投与が奨励されるエビデンスが増えた→結果、救命士の判断基準の明確化や教育体制の見直しがなされた→救急救命士による早期アドレナリン投与が重要視された内容がプロトコルに追加されて改訂・反映されている実情。
㉑アドレナリンとは、心臓の機能を高めたり、気管支を広げたり、血圧を上げたりする作用があり、アナフィラキシーショックや心停止、重い喘息発作などの緊急時に使用→一言では、「命を救う緊急用の興奮薬」。特に、アナフィラキシーや心停止などの危機的状況で使われる薬。[AIによる概要]
テレビ医療番組で『心肺停止時』によく投与されていますよね! アドレナリン投与って!!!
文章を読むのが苦手と言う方へ、街頭活動での私が指摘する救急車稼動について、話を聞いて理解願いたい。
2.今村消防長が指示した「救急救命士を合流させる運用」と「長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコル」を比較して、問題点や遵守する上で懸念される点はないのか。
①ごあいさつ
さぁ!やるか!と問題点の発「堀」作業を進めようとプロトコルを精読するのだが、私が前回ぼやいたとおり「医学小冊子」!様々な検索エンジンを活用したりするが医学用語・専門用語が多く時間ばかり浪費っ!一言でプロトコルと言っても、その時々で変わる人間の状態によって判断や処置などが手順化されており、策定された手順が幾つもある。どのプロトコルから「堀」下げてよいのか。救急隊の署員の皆さんは、この判断基準や手順のもと日々の活動をされているのです。感謝の一言であります!本当に頭が下がります。
さて、精読しても時間を浪費するばかり。今回は専門知識がある医療関係者に新たにアドバイスと説明を頂きながらも、引き続き関東地区の消防職員の方にも教示を頂けました。
精読しましたが、医療のことは医療関係者に相談した方がいい!餅は餅屋。その分野のことは、その道のプロに任せるのが一番確実で効率的という、現代にも通じる知恵であります!
五島市消防署の救急隊員の方から知恵を頂きたいのですが、幹部職員から権威による不当・強権的な弾圧を避けられない環境と察し控えております!私の調査が原因でそのような署員を生んでしまっては※「本末転倒」である。胸ぐらを掴む暴力行為事案が横行、再び起きてしまっては※「本末転倒」である!
前回アップ記事【シリーズ⑥】の文中には、「新たな問題点が浮上しつつある!救急救命士は傷病者への接触から10分以内の早期アドレナリン投与が重要だ!」と述べておりました。救急活動は時間との勝負であることは一般常識。他署所から救急救命士が合流するために出動する運用ですから、当然、合流した場合の手順はあるのか、アドレナリン投与までの10分という時間的制限と合流との関係性はどうなのか。この2点を焦点をあてキーワードとして調査開始しました。無計画で方針のない情報収集では非効率なだけで、成果や答えを導くことは難しいのである。
現場職として救急業務を日々遂行されている署員の皆さんは、長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコルは熟知しておられるはずですから、直ぐにプロトコル上の問題点はお気付きになられていることでしょう。私は、救急隊の実務に携わっていない以上、外部から得られる情報をもとに分析・考察するしかない。あくまで想像でしかないので、実際は違うかもしれませんが、私の調査結果を記していきます!
②プロトコル上における用語の関連事項
救急業務の実施に必要なプロトコル上での用語を書面全体を通読しながら精読していくと、私のような一般市民では日常生活で馴染みがない用語が文中では使われている。
119通報の入電時刻を「覚知」、現場に停車した時刻を「現着」、現場を出発した時刻を「現場発時刻」、患者に触れて観察を開始した時刻を「接触」、救急車の現場発から医療機関到着までの時間を「搬送所要時間」、傷病者接触から車内収容までの活動を「現場活動時間」と言うなど時刻の項目は、はっきり用語が区別され記されている。また、場所や活動の項目についても「病院到着」、「搬送中」、「搬送に移る」、「車内活動」、「※現場」などはっきりと用語が区別され記されている。
その他、防災航空隊にあっては、「現場に停車した時刻」とあるのは「現場上空に到着した時刻」と読み替える。
当然、生命に関わる判断と処置をするための基準と手順が記された重要なプロトコルなのだから誤解釈がないよう区別されているのだな。というのが私の率直な感想である。一貫性がある!医療分野における誤解釈防止のためには欠かせない用語の区別なのだろう。いかなる場合も医療ミスは許されないのだから。
③【アドレナリン投与プロトコル】を一部公開。[長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコル]
救急救命士が医療行為として薬剤を使用する際の具体的な適応条件・投与量・手順などを定めたマニュアル(指針)。これは法律・厚労省通知・長崎県メディカルコントロール(MC) 体制によって厳密に管理されております。[Webサイト引用]


※抜粋文面
【注1】心電図モニター波形がショック非適応リズムの場合、可能な限り現場でアドレナリン投与を行う。
救急救命士は傷病者への接触から10分以内の早期アドレナリン投与が推奨されていることは調査で判明している。このプロトコルには「可能な限り現場で行う」とされている。両者が紐付けされた意味合い(本意)なのだろうか!?
この適応条件下での注意書き(投与場所の制約)には、私は読解のポイントとして気づきがあった。この適応条件下での「現場」とは、どこの場所を指すのか?合流する運用をするのだから、当然に合流場所も現場に含まれるのか?救急車は走行する車両であるのだから、一言で現場と言っても、救急隊の皆さんは活動している現場が移動することになりませんか!?プロトコル上の「現場」とは、どの場所を定義し指しているのだろうか!?
私は、規定に基づく事項のみを信頼の拠り所とする絶対主義であり調べてみた!
④プロトコル上の「現場」とは?

〇五島市消防救急業務規程
第2条(3)[定義]
救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
◯Webサイトでの検索結果
「救急現場」とは、「現場 → 搬送中 → 病院到着」という一連の流れすべてが 救急の現場 です。
結果、比較してみたのだが、「現場」には、広義と狭義での意味が存在する。どちらの表現も一義的ではなく、2つの意味のどちらもアドレナリン投与適応条件下の注意書きが示す「現場」として解釈可能。
救急車は移動する車両であるのだから、搬送中の傷病者がある場所(救急車の車中)も「現場」を指す可能性がある。私の見解上は、プロトコル上における用語は文章全体を通読した限りは、はっきり用語が区別され記されているのだから、このプロトコル書面上で示された「現場」とは 狭義での意味合いではないのか!?。つまり、可能な限り現場でアドレナリン投与を行う。とされる「現場」は[最初の発生場所] を意味すると解釈しているのだが、専門ではないがゆえ確信は出来ないのである!
プロトコル上の、「可能な限り現場でアドレナリン投与を行う。」とされている現場には、合流場所を含むのか?私が最も疑問視した点。
⑤他の自治体消防職員への問い合わせ[関東地区の消防署に勤務しておられる方]
Q.先日は救急医療体制についてに、貴重な情報をありがとうございました。お手数をおかけして恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。貴殿の都道府県で策定されておりますプロトコルが、長崎県と相違がある旨は承知した上で2点ほどお伺いします。
長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコルの中には、アドレナリン投与プロトコルがございます。適応条件下での注意書きとして、「【注1】心電図モニター波形がショック非適応リズムの場合、可能な限り現場でアドレナリン投与を行う。」と記されております。
〇プロトコル上の現場とは、広義の意味での現場(病院到着までの救急隊の一連の流れすべて)、もしくは、狭義の意味での現場(救急業務の対象となる傷病者がある最初の発生場所。例えば自宅など。どちらの解釈で受け止めて理解してよろしいでしょうか。
〇プロトコル上での「現場」の解釈を踏まえた上で、仮に同一事案の同一傷病者1名に対して救急車2台が最初の発生場所以外で合流した場所(合流場所)は、「可能な限り現場でアドレナリン投与を行う。」とされている現場に含まれますか?ご確認をお願いしたく、該当書面をお送りいたします。
A.ご返信遅くなりました。アドレナリン投与プロトコル上の「現場」の解釈ですが、119番の救急要請により救急小隊が到着した場所です。例を上げますと、交通事故の発生した場所や自宅、公共の場など救急小隊が出動して傷病者の目の前に到着した場所。お見込みのとおり、最初の発生場所 を現場として扱います。
広義の意味での現場とは分けて考えて下さい。
救急小隊間での合流場所については、念のため送付頂いたプロトコルを自局の救急課長にも確認しました。救命士の早期アドレナリン投与が重要視され全国的にプロトコルに追加された現場とは、最初の発生場所です。合流場所をアドレナリン投与プロトコル上の【注1】の現場には含んではいけません。合流場所は最初の発生場所でないため、プロトコル上の現場には含まれません。その解釈を誤ると統一された判断基準や処置手順が混乱してしまいます。プロトコルを解釈する上で合流場所を現場と扱ってはダメですね。
言葉を借りて説明しますが、より早い時期にアドレナリンを投与する方が薬の作用や高い効果が期待できるから、最初の発生場所を現場と定義している。とでも理解して下さい。
先日お伝えしましたが、自局は、同一事案の同一傷病者1名に対して指令センターが2つの救急小隊を出場させることはしておりません。救急小隊とDr.ヘリやDr.カーが合流することは度々あります。よろしいでしょうか?
3.問題点の深「堀」り!
※重要なところだと、私は考えておりますのでプロトコル上の用語の区別、消防長通知(合流)の文面を、意図的に盗用・混合して架空の事例を設定し記述します。
①事例1から検討。
CPA(心肺停止) などの特定行為が必要な傷病者だと思われる119通報を入電「覚知」し、現場の管轄区域を所管する出張所の救急隊Aが出動。患者自宅の駐車場付近に停車「現着」し、自宅の台所に倒れていた患者に触れて観察を開始「接触」。この出動した救急隊Aには救急救命士が不在のため、管轄区域外の他署所から救急救命士を合流させる目的で救急隊Bも出動した。病人を「搬送中」の救急隊Aと、他署所から来た救急救命士を乗せた救急隊Bが搬送中の道路で合流した。救急隊Bの救急救命士が、救急隊Aの救急車に乗り込み病院へ搬送し病院到着した。

Q. プロトコルには、【注1】心電図モニター波形がショック非適応リズムの場合、可能な限り現場でアドレナリン投与を行う。と判断基準や手順が定められいます。遵守しなければなりません。では、合流した救急隊Bの救急救命士が、可能な限りアドレナリンを投与しなければならない現場はどこですか?次のうちから選べ。
⑴最初の発生場所(自宅の台所)
⑵ 救急隊Bの救急救命士が、救急隊Aと合流した搬送中の道路(合流場所)
⑶ 【注1】に規定する可能な限りアドレナリン投与を行う現場は無い
私自身がプロトコルを精読して得られた用語の解釈・知識と、問い合わせ調査結果を照合して、事例1を解いていく!あくまでも、アドレナリン投与プロトコル【注1】の規定に限定して切り抜き解いていく!私は文脈や文章構成・構造を探り読解するのは得意なのだが、医学分野は無知な者であり、医学的説明はできません。
この事例の救急隊Aと救急隊Bにとって、プロトコル上の現場の定義(概念)は、最初の発生場所である。つまり、「患者自宅の台所」。救急隊Aが搬送中に救急隊Bの救急救命士と合流した場所は、「現場以外の単なる合流した道路」というだけで、合流場所をプロトコル上の現場として解釈するのはNGである!
答えは、⑶ 【注1】に規定する可能な限りアドレナリン投与を行う現場は無い。と私は導き出した。
②答えを⑶と導いた私の見解と理由???
本来、同一事案の同一傷病者1名に対しては、一般的に1つの救急隊が1台の救急車で出動して、最初の発生場所の現場に必ず到着するのは誰でもわかる。しかし、この事例は、救急隊Aには最初の発生場所である「現場」が存在する一方で、救急隊Bは最初の発生場所の現場に到着していないのだから「現場」は存在しない。救急隊Bに存在するのは、現場以外の単なる道路。つまり、救急隊Bには「合流場所」はあるが「現場」は存在しない。
よって、この事例の救急隊Bの救急救命士にとっては、可能な限りアドレナリン投与を行う現場が無い、存在しないことになる!
これでは、規定された遵守基準が、実効性を失い形だけの存在になり実質的な意味を失っている。形式的にはルールや基準が存在するが実際にはそれが意味をなしていない、基準があっても有名無実となる状況に陥ってしまう。プロトコル上の「現場」という用語の区別が形骸化しており、一貫性がある単一のプロトコルの基準から、複数の誤認が同時に派生して見解の不一致が生じてしまう。文章構成に整合性があるように定義・対象・適応・範囲など明確化されたプロトコルの解釈が不一致となり救急活動の判断や処置に迷いが生じてしまっては※「本末転倒」である。判断の迷いは死に直結するのである。
2台の救急車を合流する運用をしてしまうと、救急業務の実施に必要なプロトコルの遵守すべき判断基準や手順が、実際の救急救命士の活動と矛盾が生じる。遵守すべき判断基準や処置の手順が曖昧・うやむや、となりますね!その悪影響は最終的に市民の生命を左右することになるのです。

今村消防長お殿様は、組織内で発生した非違行為や信用失墜行為など公務員のモラルに関する問題を、うやむやにするのが相変わらず得意のようだが、投機的な合流運用を開始して、長崎県統一の救急業務の実施に必要なプロトコルまでも、うやむやにするのですか!?立派な宝刀をお持ちだ。
③ 実は答えはカンタンなのだ![私の本音を暴露(笑)]
実は、答えを導く最大のヒントは文脈の中にあるのですよ!法律実務に詳しく精通した人物、法律文書の読解に長けた人物にとっては、プロトコルに規定する内容と、合流運用の問題点の発「掘」作業は、意外とシンプルです!さほど困難ではない。法律文書に特有の構造的・論理的特徴、法律的な記述における一貫性・用語の使い方・文体などの特徴を理解した人物にとってはカンタン!さぁ種明かしの時間です!私は、記事文中に小細工を意図的に記述しておりました(笑)気付いた貴殿は、法律実務の経験が豊富な方でしょうか。余計な詮索や推測に走らず、条文の構造・文脈・定義を重視して読解できる方ですね!


※ 長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコルの一部抜粋添付します。
【防災航空隊にあっては、「現場に停車した時刻」とあるのは「現場上空に到着した時刻」と読み替える】

このように、読み替え対象が具体化され明確に設定されていますね!「読み替え規定」とは、解釈の混乱を防ぐため、矛盾を解消して一貫性を持たせるため、法律や規定において、ある条文や語句を他の文脈に適用する際に、文言や意味を一部変更して適用することを定めた規定のことです。法律文書や正式な文書などで使われる表現であり、原文の語句を別の語句で置き換える明確な指示である。こういった読み替え規定は法律・政令・省令などの階層的な文書に多く見られます。法律に一貫性・解釈の統一をもたらす手法は他にも、準用、準則、参照規定、定義規定など様々な方法があります。
矛盾があるプロトコルでは運用が困難になります。基準や手順の目的達成が妨げられますから。プロトコルが人命を守らないための手順書 になっては※「本末転倒」である!
例えば、【「2つの救急隊が現場以外の場所で合流した場所」とあるのは「可能な限りアドレナリン投与を行う現場」と読み替える】と、仮に読み替え規定が明確に設定されていれば、合流場所が現場の範囲とみなされる。しかし、そのような読み替え規定は、長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコルには明記されておらず未規定事項。
規定していないのだから、【注1】に規定する可能な限りアドレナリン投与を行う現場と、合流場所は不一致なのだから、この節の規定は曖昧、うやむやな判断基準となるわけです。つまり、明確な読み替え規定がないことは、可能な限り薬を使いさないという場所の制約が不明瞭。可能な限り薬を投与しなければならない適応条件下の現場が、仮に合流場所であった場合には、どこでアドレナリンを投与しても構わない、投与しなさいと指示する場所はどこでも良かっ!となるのです。
これでは重要視されている早期アドレナリン投与の有効性は遠い国の話となる。
助かる生命も助からないことが懸念される。

今村消防長お殿様が、プロトコルを熟知した上で、この合流通知を発出していないことが善(よ)〜くわかりませんか?市民目線では、救急救命士が合流してくれるのは、聞こえは良く響きは良くナイスアイデアと抱かせる対策だが、蓋を開ければ風変わりで独特で奇抜な発想で、時代の流れに逆行した私ら市民の生命を危ぶませる合流運用ではないか!【プロトコルを人命を守らないための手順書にする運用】を開始したのは今村消防長お殿様、あなたですよ!
4.確認問題!
ここまでの記述を読まれた上で確認問題です!答えを導き出して下さい!
事例2
婚姻関係にある公職の立場にある出口太市長(男性)がプライベートだからと、同じく公職の立場にある洋子(女性)に会いたくて、洋子の勤務先の「坂の上の失楽園」で密会(不倫)をしていました。2人は不倫に夢中となり、洋子が失楽園入居者の介護、見回りを怠ったことが原因で入居者のKさんの心臓が止まっていました。救急救命士が不在の救急隊Aが出動し失楽園に到着。Kさんを乗せて〇〇病院へ向かった。病院へ向かう途中、別の救急隊Bが「崎山の秘密基地」で合流し、救急隊Bの救急救命士が救急隊Aの救急車に乗り込み〇〇病院に向かった。
Q.合流した救急隊Bの救急救命士が、可能な限りアドレナリンを投与しなければならない現場は、プロトコル上どこですか?
A.答えは、言わずともカンタンですね。決して五島コンカナ王国ではありませんよ!
5.まとめ
「救急救命士を合流させる運用」と「長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコル」を比較しての問題点、遵守する上で懸念される点。
1点目:救急救命士による早期のアドレナリン投与は、救急救命士は傷病者への接触から10分以内の早期アドレナリン投与が重要であり、心肺停止患者の救命率向上や脳機能の予後改善に繋がるものとして国が見直し、プロトコルに追加され改訂・反映されている実情の中、他署所から救急隊を合流させる運用は、プロトコルの軽視、無視、逸脱していることになる。
最新版プロトコルを厳格遵守することは、助けるための最善の手順を実施することになり、それによって救命という最大の目的達成をもたらす最善の方法である。
合流しても救急救命士が合流できるのは必ず10分以内とは限らない。
2点目:実現可能な余力救急救命士のローテーションの調整を現在の調整範囲【岐宿出張所のみ】から全ての出張所に拡大すること、救急救命士として資格を活用していない特別待遇者の資格運用を行い、最初から救急救命士がいる勤務の調整に方針転換しない限り、合流を運用する限り、長崎県版救急業務の実施に必要なプロトコルを※人命を守らないための手順書と化している。
3点目:規定されたプロトコル遵守基準や手順が実効性を失い、形だけの存在になり実質的な意味を失う。
4点目:一貫性がある単一のプロトコルの基準から、複数の誤認が同時に派生して見解の不一致が生じてしまう。文章構成に整合性があるように定義・対象・適応・範囲など明確化されたプロトコルの解釈が不一致となり救急活動の判断や処置に迷いが生じ、そこから生まれた判断の迷いによって、市民の死に直結する可能性がある。
その他にも、合流する運用がプロトコルとの整合性がない問題点や看過できない点もあるのだろうと思っております。それは日夜を問わず走っている救急隊の署員の皆さんが最も事情に通じていることでしょう。

今村消防長お殿様が決定し、現場職の署員に一方的に通知したとされる「救急救命士が乗っていない救急隊に対して、管轄区域外の他署所から救急救命士を車両で運び合流させる運用は、長崎県統一の救急業務の実施に必要なプロトコル手順に反する!調和しない!本末転倒な決定である。まさに、投機的である!
救急業務に関して最新版プロトコルの手順を超える最善の救命方法や活動手順は存在していない。逆に存在していた場合それは旧版となるのだから。
最新版プロトコルの遵守に懸念点、つまり問題がありながらも運用をすることは、最善策ではなく救命率を低下させる、助かる生命も助からない結果を招く。「※救急医療の最新版」には、それ相当、当然とされる範囲の価値や意味があるのですよ。
最新版プロトコルをスルーしている間に世界は何周も回っています。

飲食を伴う公務接待観光に欲に負け、製造した過積載仕様の自慢の消防車両は最新式を発注してませんか!?エンジンもボアアップした最新式のエンジンでは!?
最新の救命するための判断基準や手順の虎の巻とも言える最新版プロトコルを逸脱し、救急業務を実施する選択肢は、市民の生命に直結するため、紛れもなく大問題である。
最新医学をひっくり返す、否定する、無効にする運用であると今回、素人の私がプロトコルを「堀」下げ、合流運用が想像の斜め下をいく対策と感じる。未来の教科書に載るレベルだ。
医学は、数え切れないほどの臨床データと科学的検証に基づいて積み重ねられてきた知見の集大成です。個人的考えや投機的な場当たり策で、それを否定しようとする行為は、地図を持たずに航海するようなものです。根拠なき主張は信念ではなく、ただの無責任な想像にすぎません。医学を覆そうとするのであれば、同等か、それ以上の根拠が必要ですが、今村消防長お殿様は説明できますか。
世の中には古い物を好む方もいますが医療は物ではなく、提供されるならば最新の医療や最新ガイドラインに基づいた救急行政サービス、処置や治療を誰でも受けたい。生命を落としてまで昔の医療での処置や治療を誰しも受けたくはないですから!
リーダーのアップデート拒否は、組織のスローダウンの保証、現場での炎上を約束するサインです!リーダーが進化の炎を消す消火器になっては本末転倒!進化を拒むリーダーは、もはや”動かぬ壁”である!
「合流対策」、どうやら今村消防長お殿様が本質的な問題を巧妙に隠すための隠蔽工作だったようだ!現場職の署員の皆さん、リーダーがどれだけ硬い盾でも、矢は放ってナンボです!真っ直ぐ放ちましょう。
6.次回
果たしてシリーズ完結編は来るのだろうか。
この居住地域による救急行政サービスの格差問題について、現場職の署員の皆様にとって最善策とは何か、お考えを聞いてみたい。合流に賛同していらっしゃいますか?
次回の内容は非公表とします。別件を調査継続中であります!
7.ぼやき
①五島市消防署、川口消防署長が部下の胸ぐら掴んだ暴力行為への情報提供を求めております。被害者に代わって被害申告(刑事告発)を検討しております。事件の詳細が分かれば訴えてあげれます。市役所でも同様の暴力行為が発生しましたが、公務員犯罪の処分の甘さと処分の公平性の欠如を感じております。
被害者の救済を第1に考えております。消防や警察は上下関係が非常に強いイメージがあり、特に消防は市町村職員である。異動しても人間関係のリセットが無く、何十年もパワハラ加害者と被害者の人間関係が続くの環境。被害者救済に情報提供をお願いします。情報提供に関しては必ず守秘をお約束します。

 求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供
求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供